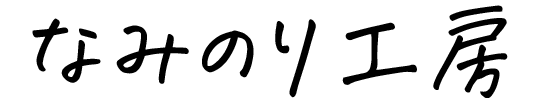たまたまサーフィン雑誌を見ていたら、この本のことを知ってしまった。
タイトルに惹かれてポチっと。
中身を想像しながら到着を待った久しぶりの本となった。
自分の将来や、この本から受けた憧れのようなものが出てきました。
そんな偶然出会った本の話書いています。
父の死から物語は始まった
新卒で入社した会社を1か月で辞めてしまう主人公の文哉と北海道に住む姉の宏美。
ある日突然、覚えのない電話番号から携帯電話に着信があり、見知らぬ男から父親の芳雄の死を知らされる。
ぶっきらぼうなその男は、父親の友人で和海という男。
3年近く父と会っていない文哉と和海とのやりとりで、父の移転後の生活が炙り出されていきます。
父の思い出を処分しようとする子供達
文哉が小学校の頃に両親は離婚してしまい、二人の子供を引取る父芳雄。
男手一つ子供を育てる父の背中は、何処かつまらない人生に文哉には写ってしまっていた。
疎遠になりかけていた父親の突然の死の知らせで、姉弟が初めて父の新しい暮らしを目にすることに。
最初は家に財産が残っていないか、早く家や車も処分してしまい遺産として処理してしまおうと考えていた姉弟でした。
ずっと自分押し殺し、自分だけの闇を抱えるようにして寡黙に働いた父親が選んだ土地、環境、周囲の人たちとの関係が徐々に見えてきます。
父が暮らした家に何度か通ううちに気持ちに変化が
父が人生を終えようと選んだ土地は、房総半島の先端にある別荘地だった。
文哉は二度目に訪れた時に、そこが海の直ぐ近くだということを発見する。
ぶっきらぼうな和海から父親が学生時代に海の家でアルバイトに来ていた土地だと聞かされる。
そして物置小屋からサーフボードを見つける。父のものだった。(ここ大事です。笑)
疎遠になっていた父の素顔を知らない文哉が遺品を整理するうちに、生活、生業、友人関係を知るうちに、父の素顔を殆ど知らなかったことに気付く。
後ろめたさを感じながら「幸せの尺度」について考えさせられていく。
千葉の田舎の海辺の村で、東京とは違う時間を生きるうちに、「幸せに絶対はないのだ」ということに気付く。
青二才だった文哉が父に言い放った言葉「他人にどんなに評価されようが、自分で納得していない人生なんて全く意味がない」そして「職業や職場を選ぶ前に、決めておくべき生き方があった」ということに。
本書から自分と重なる部分を考えてみた
父親の芳雄とワタシはほぼ同世代だと思います。
50過ぎで長年勤めた不動産会社を辞め、田舎の町へ移り住む。
彼が青春時代の夏を過ごした場所で人生をリセットする。
子育ても終わり、息子から言われた言葉に憤りを感じながらも、自分自身を生きようとした行動を、「さあやれ」と言われても出来るものではないかもしれません。
海の近くでサーフィンしながら、海の恵みをいただき、便利屋を生業として生活をしていた父芳雄さん。
息子の文哉も和海から魚や貝の捕り方を教わり、切迫する失業中の食事事情を乗り切る強さを感じ始めます。
好きなことをして生きていくということは、周りを意識する生活ではなく、自分が本気で好きなものに囲まれて生きること。
それは稼ぐというものではなく、自然に生かされながら、与えられたものだけで生きていくことで、じゅうぶんであるように思えて来るものがありました。
多分、ワタシにもできそうな生活であるように思いました。
まとめ
亡き父が暮らした家を整理することは、生前の父と向き合うこと。
遺品がかつての持ち主について語りかけてくる。
その声に耳を澄ますことが、遺され者に課せられた役目であり、遺された者ができる数少ない行いである。
そのことにようやく気付いた文哉青年は、父の辿った生き方を受け継ぎ始める。
一つの家を巡り、次第に生きる価値観の変化が少し切なく、羨ましくもあり、最後は絶対そうするよねという共感で終わりました。
自分の将来や、この本から受けた憧れのようなものが出てきました。
そして本書の最後に書かれている言葉。
幸せとは何か?それは他人に選んで貰うものではなく、世間に合わせるものでもない。
それを決めるのは、広い世界中でただ一人、自分自身にだけ許された特権なのだ。
幸せの選択と子孫に遺品を整理してもらい、共感してもらえるものを残すことができるのか?
自分の生き方を貫いた者だけが残せるように思います。
何よりも海辺の村で、ゆっくり流れる時間を過すことが、自分にとって悪いわけがないと思う、今日この頃です。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。
小学館 (2017-08-08)
売り上げランキング: 1,177
via PressSync